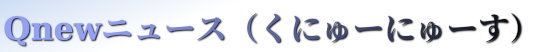

| ホーム |
|
エルニーニョ速報 1月のエルニーニョ監視海域(ペルー沖の海域)は、基準値より0.4℃低い海面水温になりました。気象庁はエルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない「平常の状態」であると判断しました。 今後の見通しについては、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)で、夏にはエルニーニョ現象が発生する可能性が高くなる(60%)と判断しました。 *2026年2月10日、気象庁発表「エルニーニョ監視速報」より *エルニーニョ監視速報は、大平洋赤道域・東部の海洋(俗に「ペルー沖」と呼ばれる海域)の状況です 海面水温・基準値との差 2025年9月…0.5℃低い(-0.4℃) 2025年10月…0.5℃低い(-0.5℃) 2025年11月…0.5℃低い(-0.5℃) 2025年12月…0.6℃低い 2026年1月…0.4℃低い *過去5ヵ月。カッコ内の数値は5ヵ月移動平均値。気象庁では海面水温の5か月移動平均値が、+0.5℃以上となった場合をエルニーニョ現象、-0.5℃以下となった場合をラニーニャ現象としています エルニーニョ現象 大平洋赤道域・東部(日付変更線付近~南米のペルー沿岸)の海域で、海面水温が平年に比べて高くなり、その状態が1年程度続く現象。逆に、平年より低い状態が続く現象は「ラニーニャ現象」と呼ばれています。 エルニーニョ現象が発生すると、東アジアでは西太平洋熱帯域の海面水温が低下し、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となります。 日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が低く、日照時間が少なくなる傾向にあります。また、西日本日本海側では降水量が多くなる傾向にあります。一方、冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温が高くなる傾向にあります。 このため、エルニーニョ現象が発生すると、日本では「梅雨が長引き、夏は冷夏、冬は暖冬になる」と言われています。 顕著な例は1993年と2009年。1993年の夏は大冷夏となり、稲作が全国的に不作となりました(1993年の米騒動)。2009年の夏はアジア全土で多雨、西日本で長期的な豪雨となりました。 ラニーニャ現象 大平洋赤道域・東部(日付変更線付近~南米のペルー沿岸)の海域で、海面水温が平年に比べて低くなり、その状態が1年程度続く現象。逆に、平年より高い状態が続く現象は「エルニーニョ現象」と呼ばれています。 日本の気象庁では、大平洋赤道域・東部の海面水温が、基準値と比べ、5ヵ月移動平均値で-0.5℃以下となった場合、ラニーニャ現象が発生としています(速報の場合)。 ラニーニャ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が上昇し、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が活発となります。 このため、日本付近では、夏季は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向にあります。 また、沖縄・奄美では南から湿った気流の影響を受けやすくなり、降水量が多くなる傾向にあります。 冬季は、西高東低の気圧配置が強まり、気温が低くなる傾向にあります。このため、日本では「夏は猛暑、冬は寒冬になる」と言われています。 *参考…気象庁・ラニーニャ現象、エルニーニョ現象について |
|
|
 |
|
|
|
|