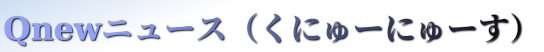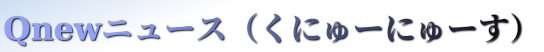|
|
|
|
|
|
|
日本の総資産は1京4119兆円(前年比4.0%増)。内訳は非金融資産が4011兆円、金融資産が1京108兆円です。詳しくは「日本の資産状況」へ
・日銀は10月30日の金融政策決定会合において、日本経済は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」と判断しました(前回と同じ)。今後の見通しについては「海外経済の減速を受け、成長ペースは伸び悩む」と判断しました(前回と同じ判断)。詳しくは「日本の景気」へ
最新の失業率は「2.6%」です。詳しくは「雇用・物価情勢」へ
最新の物価(インフレ率)は+3.0%です(12月19日発表)。詳しくは「雇用・物価情勢」へ
2次産業(生産)は「一進一退」。3次産業は「一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動き」。詳しくは「日本の景気」へ
・安定したインフレ率2%を目標に、日銀による金融緩和が行われてきましたが、「物価安定の目標」が実現する見通しになったことから、2024年3月より金融緩和の縮小に入りました。
2024年3月19日、日銀・金融政策決定会合で日銀当座預金におけるマイナス金利を解除。資産買入れのうち、ETFおよびJ-REITの新規買い入れを中止し、CP等や社債等も買入れ額を段階的に減額し、1年後をめどに買入れを終了することが決まりました。
2024年7月31日、日銀・金融政策決定会合で政策金利(無担保コールレート)を0.25%に引き上げ、国債買い入れを3ヵ月毎に4000億円程度ずつ減額していくことに。さらに2025年1月24日に0.25%引き上げ、2025年12月19日にも0.25%引き上げました。現在の政策金利は0.75%です。
詳しくは「政策指標」へ
国際収支(経常収支)は円安の影響で、武漢肺炎前を上回る黒字となっています。詳しくは「国際収支」へ
|
|
|
|
|
|
|
経済指標は「失業率」と「インフレ率」が最重要視
アメリカが最初の金融緩和(QE)を行なったとき、この2つの数値が「金融政策決定の指標」となりました。
以降も、失業率(雇用統計)とインフレ率(物価)がアメリカの金融政策を決める最重要指標であるとともに、目標(雇用最大化とインフレ率2%)にもなっています。日本においても「失業率」と「インフレ率」が経済対策・金融対策の最重要指標となっています。
なお、最近は特に失業率(雇用統計)が最重視されています。
日本の物価は原油価格に大きく左右
原油をほとんど生産しない日本は海外、特に中東からの輸入に頼っていますが、原油価格は不安定な世界情勢を受け、乱高下を続けています。このため、日本経済は原油価格に一喜一憂する形となっています。
為替の影響も大きい
日本経済は「為替の影響」を大きく受けます。まず、貿易収支(経常収支)に大きな影響がでます。さらにインフレ率や失業率にも大きな影響が現れます。
円高が進むと、これに応じて輸入品の価格が下がり、日本の国内物価(インフレ率)も下落傾向となります。円高は輸出悪化や海外からの旅行者減少につながり、雇用状況を悪化させます。
|
|
|
|